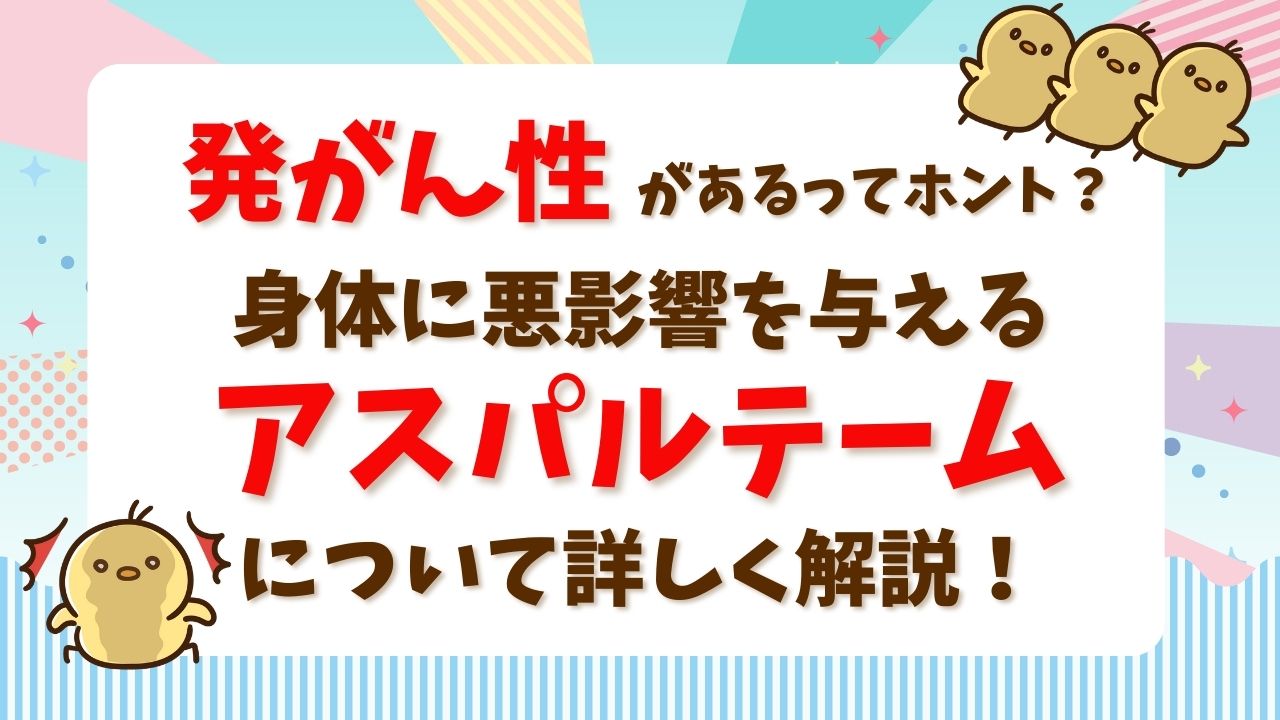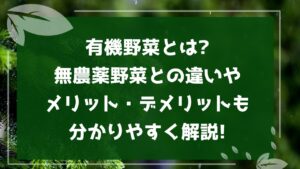「糖質オフ」「カロリーオフ」
そんな表記を見ると、何となく健康にもダイエットにも良い気がして、手にとってしまうことはありませんか?
ですがそのような商品には、砂糖を使わずに甘くするために、身体に悪影響を与える可能性があるアスパルテームという化合物が使用されているかもしれません。
 ひよこ君
ひよこ君アスパルテームって最近ニュースで見たような気がする…何だっけ?



最近、「発がん性リスクの可能性がある」って発表されたことが大きな話題になったんだよね。



発がん性!?それって結構やばいんじゃ…



確か、日本で売られてる商品にも結構入ってましたよね?



そうだね。もちろんまだ断定されたわけじゃないし、可能性の段階なんだけど、気をつけた方が良いという事には変わりないからね。
今回の記事では、日本でも広く使われている人工甘味料のアスパルテームについて、詳しく紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。
アスパルテームとは?
アスパルテームとは人工甘味料の一種で、日本でも多くの商品に使われています。
アスパルテームは、砂糖の主成分であるショ糖とカロリーは同じですが、甘味はショ糖の約100~200倍とされています。少量で強い甘味を実現できるアスパルテームは、ダイエットを謳う食品や人工甘味料などに幅広く使用されてきました。



アスパルテームは人工甘味料だから、自然界には存在しない化合物なんだ。少量でかなりの甘みを感じることができるから、お菓子や清涼飲料水の原材料としてよく使われているんだ。



コンビニに売られているほとんどの清涼飲料水に使われているって聞いたことがあります。



なるほど。日本でも一般的に使われているってことだね。
砂糖をアスパルテームに置き換えるメリットとして、主に次の2点があげられます。
- 血糖値の上昇を防ぐ
- 虫歯のリスクを減らす
一方で、過剰に摂取すると次のような副作用を引き起こす可能性があるというデメリットも存在します。
- 頭痛
- めまい
- 消化不良
妊娠中や授乳中の女性、特定の遺伝子異変を持つ人にとっては危険であり、摂取をさけるべきとされています。
アスパルテームは発がん性があるって本当?
最近アスパルテームが注目を集め出したのは、その発がん性の危険性が指摘され出したことがきっかけです。
アスパルテームに発がん性はあるのでしょうか?



実際に日本でも多くの商品に使用されているのに発がん性リスクが指摘されたのは大変なことだよね…



さっきも話したように、確定ではないからね。
今はまだ発表元であるWHOと専門家の間でも見解が分かれているんだ。
それぞれの見解を見ていってみよう。
世界保健機関(WHO)や食品医薬品局(FDA)の見解
世界保健機関(WHO)は、アスパルテームの発がん性の分類を「発がんの可能性がある物質」に指定しました。これは1,300の研究論文などを元に調査を進めた上で発表を行ったと言われています。
但し、一般的に使用されている量のアスパルテームに関して安全性には大きな懸念はないと主張しています。あくまで1日の摂取許容量を40mg/kgとし、常習性がある、または許容量を超過した摂取が行われる場合においてリスクがあると判断されているとのことです。
アメリカの食品を取りしまる政府機関である食品医薬品局(FDA)も、アスパムテールの1日の摂取許容量を50mg/kgとし、適切な摂取量であれば、安全性に問題はないとしています。
WHOやFDAが示すアステルパームの1日摂取許容量は、清涼飲料水を20杯近く飲まないと超えないことから、普通に生活していえれば、超えることは考えにくい量です。



何事も限度がある、という話ですよね。



その通り。どんな原材料だって致死量というラインは存在するものだからね。極端に言えば塩だって醤油だって致死量以上を摂取すれば危険なわけで、アスパルテームも許容量を守っていこうねというのが発表の趣旨だと思う。
専門家の見解
WHOやFDAのアスパルテームへのリスク評価は「適正な摂取量を守れば、安全性に問題はない」とするものですが、専門家の見解は、必ずしも一致していません。
アステルパームと発がん性の因果関係の脆弱性が指摘される一方で、日常的にアステルパームを摂取している人のがんの発生リスクが高いことを示す研究結果も示されています。



基準はあるけど、本当にその基準で大丈夫?というのが揺らいでいる感じなのかな?



元々基準値は設けてあったわけだから、WHOが発がん性リスクの指摘を行なった意図があると考えるのが自然だよね。



消費者としても避けられる範囲でなるべく避けた方が良いという認識を持って、リテラシーを高めていく必要がありますね。
アスパルテーム以外に代替できる甘味料はあるの?
専門機関によって、ある程度の安全性が示されているアスパルテームですが、それでも「発がんの可能性がある物質」を積極的に摂取することは避けたいですよね。
また、いくらここまでは安全という指標が示されていたとしても、身体が許容できるアスパルテームの摂取量の上限には、やはり個人差があるはずです。他の甘味料で代替することは可能なのでしょうか?
食品によく使われる甘味料
食品によく使われる甘味料には、他にどのようなものがあるのでしょうか?よく使われている甘味料について、紹介していきます。
アセスルファムカリウム
アセスルファムカリウムは、酢酸由来のジケテンという物質を原料として作られる人工甘味料です。こちらもショ糖の約200倍の甘味があるとされており、ノンカロリー甘味料として、ダイエット食品や清涼飲料水に使用されています。
アセスルファムカリウムは、製造の過程で発がん性のある塩化エチレンが溶媒に使用されていて、アスパルテームと同じくその危険性が懸念されます。
(参考:本当に危ない人工甘味料(その3)/くにちか内科クリニック)
カンゾウ抽出物
マメ科カンゾウなどの植物の根や茎から抽出された物質で、カンゾウエキスやリコリス抽出物などが存在します。さらにそれを抽出したものがグリチルリチンという物質です。
カンゾウ抽出物も同じく甘さがショ糖の約200倍と言われています。塩味をマイルドにしたり、旨味出しの効果があります。
清涼飲料水や菓子類だけでなく、醤油、みそ、漬物などにも幅広く使用されています。また、食品に限らず、化粧品や医薬品にも使われる成分です。
(参考:カンゾウ根 | ハーブ | 医療関係者の方へ/厚生労働省eJIM)
サッカリン、サッカリンナトリウム
サッカリンは、ショ糖の約500倍という強い甘味が特徴です。甘みが長く残るのが特徴で、粉末の清涼飲料水や魚介加工食品、缶詰など、幅広く使用されています。
ただ、サッカリンも膀胱がんの発がん性を指摘する研究結果が報告されており、安全性が気になる物質です。
(参考:本当に危ない人工甘味料(その1)/くにちか内科クリニック)
キシリトール
キシリトールは、私達にとっても聞き馴染みのある甘味料ですよね。樹木などから抽出したキシランという物質から作られます。
キシリトールは、甘さもカロリーもショ糖と同程度です。虫歯予防の甘味料として、チューイングガムやキャンディによく使用されています。小腸で消化・吸収されづらい物質のため摂取しすぎるとお腹が緩くなりやすいと言われていますが、非常に安全性は高いと評価されています。
(参考:【注意】キシリトールガムの甘い罠!!!/たきかわの森歯科クリニック)



キシリトール以外の他の甘味料も結局ほとんどが安全性に懸念があるんだね。



しかもキシリトールは他の甘味料と比べると甘さがかなり控えめになっているので、アスパルテームの代用品として考えるのは難しそうだね。
アスパルテームの代替は難しい
現状、アスパルテームを他の物質で代替するのは難しいと考えられます。アスパルテームと同様に少量で強い甘みを出すことのできる人工甘味料は、同じように発がん性などの危険性が疑われるものが多いです。
また、砂糖やはちみつで代替すると、カロリーやコストが跳ね上がってしまい、アスパルテームと同じように食品に使うのは難しいでしょう。
アスパルテームが含まれる主な製品
それでは、具体的にどのような製品にアスパルテームが含まれているのでしょうか?私達に馴染みのある製品の中でアスパルテームが含まれるものには、例えば次のようなものがあります。
コーラ
日本コカ・コーラのコカ・コーラ プラス、キリンホールディングスのキリン メッツ超刺激コーラなど
カルピス
アサヒグループ食品のカルピスソーダ®、アサヒ飲料のカラダカルピス®BIO、GREEN CALPIS、ゼロカルピス® PLUS カルシウムなど
お酒
アサヒビールのアサヒ スタイルバランスプラス カシスオレンジテイスト、サントリーのソウルマッコリ、ペプシBIG〈生〉ゼロなど
コーヒー系飲料
ネスレ日本のネスカフェ エクセラ ふわラテ、ネスレ 香るまろやか ほうじ茶ラテ、ネスレ 香るまろやか ミルクココア、味の素AFGのブレンディ® スティック カフェオレなど
調味料
味の素のパルスイート®、パルスイート®カロリーゼロ、アミノバイタル アクティブファイン、ハウス食品のスパイスクッキングオイキムチなど
お菓子
カルビーのじゃがりこ九州しょうゆ味、シンポテト 金色バター味、スーパーポテトサワークリーム&オニオン味、ヤマザキビスケットのエアリアル コーンポタージュ味、チップスターS チェダーチーズ味、ロッテのチューイングガムなど



こうして見ると家にあるものも多いですね…



そうなんだ。こんなにも身近にある物質が発がん性リスクを指摘されたという意味で、今回のWHOの発表はインパクトがあったんだよね。
アスパルテームは摂取を避けるべき?
結局のところ、アスパルテームは摂取を避けるべきなのでしょうか?
なるべく摂取しないほうが健康的である
前述した通り、WHOやFDAなどの専門機関は、アスパルテームは適正量の摂取であれば、健康への悪影響への心配はないとしています。
過度に心配しすぎてストレスをため込んでしまう必要はないと考えられますが、アスパルテームの発がん性を指摘する研究結果が出ているのも事実です。
他の添加物も同じですが、人によっても体の許容量には差があると考えられるので、できるだけ摂取をしないことが、自分の健康を守ることになるのは間違いないでしょう。




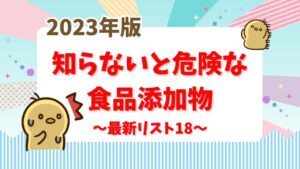
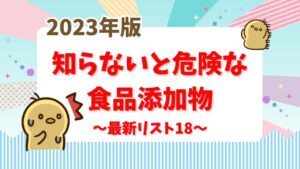
オーガニックな食生活の取り組み
健康のことを考えるのであれば、オーガニックな食生活を始めてみるのがおすすめです。
できる限り添加物の少ない食品や安全な製法で作られた食品を選んだりすることで、自分の健康と向き合った自然由来の食生活を送ることができます。
自然由来の食品の味に慣れていくと、人工的な甘味料の甘さも徐々に舌や体が求めなくなっていきます。



初めは口恋しくなるんですけど、慣れると全然ほしい気持ちがなくなってくるんですよね。



「とにかくアスパルテームを避けよう!」みたいな考えになるとストレスがたまってしまうけど、元々の食生活から改善していけば気にならないね!



オーガニックってそもそも何だっけ?という人は下の記事で解説しているから、リンクをクリックして確認してみてね!



私がおすすめしているオーガニックランチが食べられるお店もぜひ行ってみてくださいね。めちゃくちゃ美味しいですよ!




まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は、最近話題のアステルパームについて気になるポイントを解説してきました。今のところは安全だとされていますが、まだ不透明なところがありますのでできれば摂取を避けたいです。
健康的な食生活のための参考に、気になった他の記事もご覧になってくださいね。