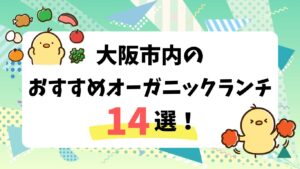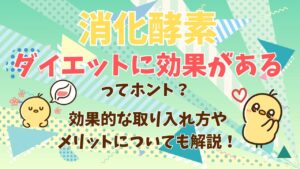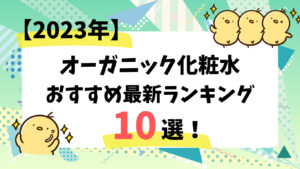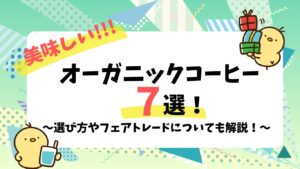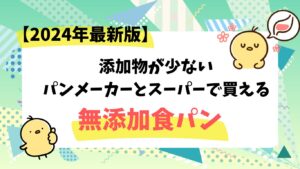「免疫力の高い健康な体づくりのためには、まずは腸内環境を整える必要がある。」
そんな話をよく聞きませんか?
 ひよこ君
ひよこ君確かに!体の調整を整えるために必要ってよく聞くよ。



私もよく聞くから腸内環境にいいって言われている納豆をできる限り食べるようにしてる!(笑)



最近は腸が注目されるようになってきて、腸活もブームとなっていますよね。
ですが、具体的にはどのようにして腸内環境を整えれば良いのでしょう?
今回の記事では、
- そもそも腸内環境とは?
- どうして腸内環境を整えた方が良いの?
- 腸内環境が悪くなるとどうなるの?
- 腸内環境を整えるためには、何を食べたら良いの?
といった疑問にお答えしていきます。
ぜひ最後までご覧ください。
今回の記事は、「健康のために腸内環境を整えたいけどどうしたら良いのか分からない」という方に向けて「腸内環境の整え方」を徹底解説しています。
腸内環境とは?


腸内環境とは、腸内に生息する細菌を含む腸の内部環境のことです。
腸内には、人間の体の細菌の約9割が生息しています。私達の小腸から大腸にかけて生息する細菌の数は、なんと約1000種類、約100兆個と言われています。
腸内細菌(腸内フローラ)とは
腸内フローラという言葉をよく聞きますよね。
正式名称は、「腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)」と言います。
腸内の細菌は、その種類や性質ごとに固まって生息しています。その種類ごとに固まった細菌の集まりが、まるでお花畑のように見えることから、「腸内フローラ」と呼ばれています。
善玉菌と悪玉菌とは
腸内の細菌には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類があります。
善玉菌は、私達の体にとって、良い働きをしてくれる細菌です。腸内で悪玉菌が増えるのを抑制したり、有害な物質を体外へ排出したりする役割を担っています。
一方で、悪玉菌は、私達の体に悪影響を与える細菌です。悪玉菌は、腸内で有害物質を作り出します。そのことが腸の炎症を引き起こしたり、発がん性物質を作り出したりして、体調不良の原因となります。
日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のうち、優勢である細菌の働きをする細菌です。そのため、善玉菌が優勢の環境では、日和見菌に害はありません。しかし悪玉菌が優勢になってしまうと、日和見菌も悪玉菌と同じ働きをするようになります。
腸内の細菌の理想的な割合は、善玉菌:悪玉菌:日和見菌=2:1:7の状態であると言われています。善玉菌が悪玉菌より優勢となり、多数派の日和見菌が善玉菌の働きをする状態が、腸内環境が整っている状態です。
腸内環境を整えた方が良い理由
そもそも、腸内環境を整えるとどのようなメリットがあるのでしょう。
腸内環境を整えた方が良い理由として、次のようなメリットがあげられます。
- 免疫力が高まる
- 代謝が上がり太りづらくなる
- ストレスが溜まりづらくなる
免疫力が高まる


腸内環境を整えることは、免疫力のUPに繋がります。感染症にかからない免疫力を高めることは、健康な体づくりに欠かせませんよね。
私達の免疫細胞の約7割が、腸の中に存在しています。ウイルスは、口や鼻から入ってくることが多いですよね。特に食べ物を取り入れる口からは、食べ物以外の細菌やウイルスが体に侵入してくる入口となります。
そのようなウイルスに対抗して体を守ってくれるのが、腸管免疫という腸内の免疫細胞です。
腸内環境を整えることで、病気になりにくい体を作ることができます。
代謝が上がり太りづらくなる


腸内環境が整うと、代謝が上がり、太りづらい体になります。
腸内環境が整うことで、腸は栄養を吸収しやすくなります。このことにより、代謝の役割を担う肝臓が効率的に働くようになります。
また、栄養や酸素を体中に運び、有害な物質を体外に排出する運搬係である血液の働きもスムーズになります。体内の栄養素が上手く循環することで、さらに代謝力が上がります。
同じ量を食べても、不要な成分を体外に排出しやすくなり、太りにくい体を作ることができます。また、代謝が良くなることで、お肌や髪もきれいになるので、総体的な美容効果が期待できます。
ストレスが溜まりづらくなる


腸内環境が整うことで、精神的にも安定し、ストレスが溜まりづらくなります。
腸と精神的な問題は、関係がなさそうに感じますよね。ですが、腸の状態とストレスには、強い繋がりがあります。
私達の脳の自律神経系は、その働きによって、交感神経と副交感神経に分けられます。交感神経は、体の機能を活発化させる神経で、副交感神経は臓器や期間などの動きを抑制する神経です。
その性質上、交感神経はプレッシャーを感じているときに、副交感神経はリラックスしているときに働きます。実は、腸はこの副交感神経が優位になったときに活発に働きます。
腸が正常に働くことで、副交感神経が優位となり、ストレスを感じにくくなります。
逆に言えば、リラックスして過ごすことが、腸内環境を整えることに繋がります。
腸内環境が悪くなるとどうなる?
腸内環境が悪い状態になるのは、腸内の悪玉菌が優勢となるときです。
まず最初に感じやすいのは、便秘や下痢、腹痛などの症状です。栄養の吸収や排便が上手くいかないことで、このような症状が起こります。



こ、これは心当たりある人も多いんじゃないかな、、、



確かに、仕事が忙しくて冷凍食品ばかり食べてたら、便秘になりがちだったな。。。
また、前述した腸内環境が整った状態で得られるメリットと逆の症状で、免疫力や代謝の低下、ストレスの増幅などが引き起こされます。
腸の炎症や代謝の低下によって体の隅々まで栄養が行き届かなくなるので、体のさまざまなところで不調が起こる可能性があります。感染症や生活習慣病にかかる危険性も高くなります。
そのような状況となるのを防ぐために、腸を整えるには、次のように生活習慣を改善する必要があります。
- 食生活を改善する
- 睡眠習慣を改善する
- 適度に運動する
食生活を改善する


まず、最初に取り組みたいのが、食生活の改善です。食事は、善玉菌と悪玉菌のバランスを整えることに直結します。
実は、日本人本来の穀物や野菜中心の食事は、善玉菌を増やして腸内環境を整えるのに適した食事です。
動物性のタンパク質や脂質、インスタント食品などを取りすぎることは、悪玉菌の増加に繋がります。



腸内環境を整えてくれる食材については、後ほど詳しく紹介していきます。


睡眠習慣を改善する


腸内環境を整えるためには、睡眠習慣を改善することも大切です。腸と睡眠は関係がないように思えるかもしれませんが、前述した通り、腸と脳の働きには深い繋がりがあります。
腸は、リラックスして副交感神経が優位のときに活発に働きます。睡眠時というのは、副交感神経の働きが優位になるときです。睡眠時間を削ったり、しっかりと眠れていなかったりして、交感神経が優位の状態が続いてしまうと、腸は正常に活動ができません。
きちんとした睡眠習慣をつけて、脳をしっかり休ませることが大切です。



ついつい夜に映画やドラマを見て睡眠時間が減ってしまってたな。。。



以下の記事では、睡眠の質を上げるための方法を解説しています。
ぜひあわせて読んでみてくださいね!


適度に運動する


適度な運動も、自律神経の働きを整えて、腸内環境を良くします。
食事、睡眠、運動が健康にとって大切なことはよく分かっているけれど、その中で1番軽視されがちなのが、運動ではないでしょうか。
運動というのは、体もきついし、時間もないし、習慣化するのが億劫なものですよね。ですが、腸内環境を整えるためには、きつい運動をする必要はありません。
激しすぎる運動はストレスとなり、帰って腸内環境を悪化させてしまいます。散歩がてらウォーキングをしたり、軽いストレッチをしたりする程度で大丈夫です。
自分が気持ち良いと思える程度の運動を、生活に取り入れるようにしてみてください。
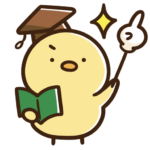
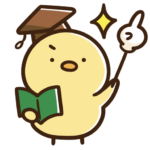
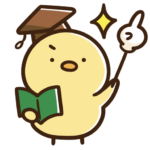
最寄駅よりひとつ前の駅で降りて家まで歩いて帰るのもよい運動になるよね!
腸内環境を整えてくれる食材
ここからは、具体的に腸内環境を整える食材を紹介していきます。ぜひ参考にしてくださいね。
ヨーグルト


「お腹に良さそうな食品」と聞いて、私達の頭に真っ先に浮かぶのが、ヨーグルトですよね。ですが、どうしてお腹によいのか、理由はよく分からないという人も多いのではないでしょうか。
ヨーグルトには、乳酸菌やビフィズス菌といった細菌が含まれています。パッケージにもよく書かれているし、聞いたことがありますよね。乳酸菌、ビフィズス菌は、実は善玉菌の一種です。
体に直接善玉菌を取り入れて、腸内の善玉菌の数を増やすことで、腸内環境を整えることができます。
納豆


あまりイメージがないかもしれませんが、納豆は腸内環境を整える上でも最強とも言える食品です。
善玉菌を増やすのに有効なのが、発酵食品と食物繊維です。納豆は、発酵食品でありながら、さらに食物繊維が豊富に含まれた食品です。
納豆に含まれる食物繊維は、水溶性食物繊維です。
食物繊維には、水溶性と不溶性の2種類があります。どちらにも長所がありますが、腸内環境を整えてくれるのは、水溶性食物繊維です。水溶性食物繊維は、大腸から余分な水分を吸収し、便の体積を増やします。
また、納豆には、食物繊維以外にも、ビタミン、ミネラル、植物性タンパク質、ナットウキナーゼ(納豆菌)などの腸内環境を整えるのに有効な栄養素が含まれています。
海藻類


海藻類も、腸内の善玉菌が好む水溶性食物繊維を多く含んでいます。
海藻に含まれる食物繊維を好むのは、善玉菌の中でも「酪酸菌」と呼ばれる細菌です。乳酸菌やビフィズス菌に比べると耳慣れない細菌ですよね。
酪酸菌は、食物繊維を発酵・分解することで酪酸という成分を作り出します。酪酸には、腸内を弱酸性に保ち、有害な菌の繁殖を防ぎます。
また、酪酸は筋肉の減少を阻止して、寝たきりになることを防ぎます。健康長寿の人の腸には酪酸菌が多いという研究結果も出ており、今注目されている善玉菌です。
味噌


味噌に含まれる酵素や微生物などの菌を体に取り入れることも、腸内環境を整える手軽な方法の1つです。動物性の発酵食品に比べて、植物性の発酵食品に含まれる菌は、生きて腸まで届きやすいのが特徴です。
味噌汁なら、毎日飲んでも飽きることがありませんよね。冷蔵庫の中の余った野菜を入れて作ることもできるし、あまり手間もかかりません。
ですが、味噌は、作り手の自由度が高く、種類も多いだけに、選ぶのが難しいという側面もありますよね。
加熱したり、添加物を加えたりしないで、1年以上の時間をかけて発酵・熟成させる天然醸造のものが、おすすめです。
麹


麹とは、米、麦、大豆などに麹菌を繁殖させたものです。日本の発酵食品には欠かせません。
麹菌が作り出す、酸性プロテアーゼという成分が、腸内の善玉菌を増やして、腸内環境を整えてくれます。さらにすごいところは、消化の過程で死んでしまった麹菌も善玉菌のエサとなるところです。
生きて腸まで届いた麹菌が善玉菌を増やして、死んでしまった麹菌は善玉菌は元気にします。両方の方面から、善玉菌をサポートしてくれる優秀な細菌です。
使いやすい塩麹を取り入れてみるのが、おすすめです。食材が持つ自然なうまみを引き出してくれて、お料理も楽しくなります。
甘酒


甘酒は、お米と麹菌をかけ合わせて発酵させた飲料です。善玉菌をサポートする食物繊維やオリゴ糖が豊富に含まれます。
また、甘酒の主原料である酒粕と米麹を一緒に摂取することで、腸内のラクトバシラス科に属する細菌の割合が増加するという研究結果も報告されています。ラクトバシラス科は、腸内の善玉菌のほとんどが属するとされている乳酸菌の属性です。
甘酒を飲むことで、腸内の善玉乳酸菌が増えて、腸内環境を整えます。
オリゴ糖を含む野菜や果物


オリゴ糖を含む野菜や果物を取り入れることも、腸内環境を整えるのに有効です。
オリゴとは、ギリシャ語で「少ない」という意味です。オリゴ糖とは、2~10個の少ない単糖から成る糖のことを指します。オリゴ糖には、善玉菌であるビフィズス菌を増やす働きがあります。
オリゴ糖を多く含む野菜には、玉ねぎ、ねぎ、アボカド、ブロッコリー、カリフラワー、アスパラガス、ニンニクなどがあります。果物では、バナナやりんごに豊富なオリゴ糖が含まれています。
また、栄養価が通常の野菜に比べて非常に高いことで有名な有機野菜は腸内環境を整える上で非常に効果的です。


大豆製品


大豆製品は、大豆に含まれる大豆オリゴ糖や食物繊維の働きによって、腸内環境を整えます。
また、大豆は腸内細菌と結びつくことで、さらに違う効果を発揮します。
大豆イソフラボンを腸内細菌が代謝することで、エクオールという女性ホルモンのエストロゲンに似た成分が作り出されます。エクオールは、女性の健康維持やアンチエイジングの役割を担います。
元々大豆製品をとることで、海外の女性と比べても日本の女性が腸内でエクオールを生成する能力は高いとされていました。ですが、食生活の欧米化にともなって、現在はエクオールを生成する能力がある若い女性の割合は20~30%と言われています。
大豆製品をとることで腸内環境を整え、腸内環境が整うことで大豆イソフラボンがエクオールを生産できるようになります。
まとめ
いかがでしたか?
何となく整えたいと思っていた腸内環境ですが、具体的にどうしたらいいかが分かりましたよね。
そんなに難しいことはなく、ただ簡単な毎日の習慣を丁寧にやっていくことが大切です。



ぜひ、腸内環境を整えて、免疫力の高い健康な体を手に入れてくださいね!